白河甚平の連載小説②
 【未来紳士】(※完結) 【未来紳士】(※完結)
 * story *
大金持ちで上品な老女が城の中で悲しい顔をしています。
それは自分の旦那さんがときどき帰ってくるのが遅かったり
城内のどこかでいなくなったりとかするからです。
きっと外に出かけているんだろう、と老女は思い
ずっと窓の外を見ながら旦那さんを待ち続けているのです。
その時、陽気な足取りでやってくる紳士が来ました。
「あなたぁ・・っ!どこにいってましたのぉ?」
老女は最高の笑顔で旦那さんを迎えました。
* story *
大金持ちで上品な老女が城の中で悲しい顔をしています。
それは自分の旦那さんがときどき帰ってくるのが遅かったり
城内のどこかでいなくなったりとかするからです。
きっと外に出かけているんだろう、と老女は思い
ずっと窓の外を見ながら旦那さんを待ち続けているのです。
その時、陽気な足取りでやってくる紳士が来ました。
「あなたぁ・・っ!どこにいってましたのぉ?」
老女は最高の笑顔で旦那さんを迎えました。
 * story *
この紳士は奥さんがいるのにも関わらずたまにしか家(城)に帰って来ない。
だがそれは、大きなわけありがあったのだ。
紳士は実は未来の人間。この世界の人間ではないのだ。
未来から過去に行くときは特殊なエレベータを使っていく。
今日も1ヶ月ぶりに嫁に会いに行く。
「ただいま。すまんな、待たせて。」
実は紳士の本当の正体は・・
* story *
この紳士は奥さんがいるのにも関わらずたまにしか家(城)に帰って来ない。
だがそれは、大きなわけありがあったのだ。
紳士は実は未来の人間。この世界の人間ではないのだ。
未来から過去に行くときは特殊なエレベータを使っていく。
今日も1ヶ月ぶりに嫁に会いに行く。
「ただいま。すまんな、待たせて。」
実は紳士の本当の正体は・・
 * story *
「おかえりなさい。前から思ってるんだけど1週間は長すぎない?
私、いつもとっても寂しい想いであなたのこと待ってるのよ」
「いやぁ〜スマンスマン・・・だがな、これは仕方がないことなんだ。」
この紳士は現在と未来を行き来しているのだ。
実際はもっと長く留守にしているのだが、
城に戻るときにタイムダイヤルを1週間後に設定している。
* story *
「おかえりなさい。前から思ってるんだけど1週間は長すぎない?
私、いつもとっても寂しい想いであなたのこと待ってるのよ」
「いやぁ〜スマンスマン・・・だがな、これは仕方がないことなんだ。」
この紳士は現在と未来を行き来しているのだ。
実際はもっと長く留守にしているのだが、
城に戻るときにタイムダイヤルを1週間後に設定している。
 * story *
未来紳士の正体はサオリという名前の女子高生。
小さい頃から魔法使いの出て来るお話が大好きだった。
ある日、一人で留守番をしているときにタンスの整理を思い立つ。
父の物が入っている引き出しもついでに整理しようとしたら、
ピカピカと異様に光っているネクタイピンを見つけた。
恐る恐る手にとってみると、
ネクタイピンから美しい魔法使いが現れた。
魔法使いが言う。
「初めまして、私は魔法使いです。
あなたは昔からずっと魔法を使って変身することを望んでいましたね?
その願いをこの私が叶えて差し上げましょう。」
「えっ、本当?」さおりの目がキラリンと輝く。
「ええ。あなたのお父様のネクタイピンに私が魔法をかけました。
そのネクタイピンは今日からあなたの変身道具です。
あなたが変身したいものを思い浮かべながらネクタイピンを振ると
あっという間に変身ができます」
「あっ、ありがとうございます!!」
「ただし、条件があります。
もう亡くなられた老婦人のお話ですが生前の頃は
とても寂しく城の中で暮らしていました。
あなたは老婦人の旦那様に変身し、
ときどきでいいので会ってあげてください。」
こうして、魔法使いがサオリの部屋のクローゼットに魔法をかけ、
クローゼットの中にできたエレベータに乗って過去に行き、お婆様と会うようになりました。
* story *
未来紳士の正体はサオリという名前の女子高生。
小さい頃から魔法使いの出て来るお話が大好きだった。
ある日、一人で留守番をしているときにタンスの整理を思い立つ。
父の物が入っている引き出しもついでに整理しようとしたら、
ピカピカと異様に光っているネクタイピンを見つけた。
恐る恐る手にとってみると、
ネクタイピンから美しい魔法使いが現れた。
魔法使いが言う。
「初めまして、私は魔法使いです。
あなたは昔からずっと魔法を使って変身することを望んでいましたね?
その願いをこの私が叶えて差し上げましょう。」
「えっ、本当?」さおりの目がキラリンと輝く。
「ええ。あなたのお父様のネクタイピンに私が魔法をかけました。
そのネクタイピンは今日からあなたの変身道具です。
あなたが変身したいものを思い浮かべながらネクタイピンを振ると
あっという間に変身ができます」
「あっ、ありがとうございます!!」
「ただし、条件があります。
もう亡くなられた老婦人のお話ですが生前の頃は
とても寂しく城の中で暮らしていました。
あなたは老婦人の旦那様に変身し、
ときどきでいいので会ってあげてください。」
こうして、魔法使いがサオリの部屋のクローゼットに魔法をかけ、
クローゼットの中にできたエレベータに乗って過去に行き、お婆様と会うようになりました。
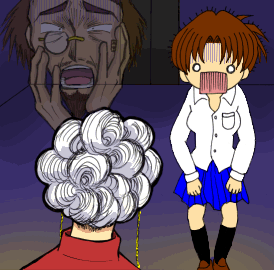 * story *
サオリは何んにでも変身できる
ちょっと変わった高校二年生。
今日は部活のミーティングが長引いて、
窓の外はすっかり夜。それでもって壁の時計はもう6時。
「大変〜!またこんな時間になっちゃった。
もうっ、今日こそは、絶対おばあさんの所に行ってあげようと
思っているのにぃ・・・
でもでも、遅くなっても今日こそ行くぅ〜
今日こそ行ってあげないと可哀相だもん」
サオリはいつも一緒に帰る友達に、
急いでいるのゴメン!!と片手で詫びて走っていった。
夜道に並ぶ街灯を通り過ぎて数分、左手方向に
2階建てのサオリの家が見える。
玄関で脱いだ靴を跳ね飛ばし、
サオリは階段を駆け上がり自分の部屋に飛び込んだ。
魔法を使っているところを誰かに見られたら、
もう二度と魔法が使えなくなる。
慌ててカーテンを閉め、両親が留守なのを確認し、
例のネクタイピンをスカートのポケットの中から取り出した。
サオリは腕を伸ばし、
円を描く様にネクタイピンをつかんだ手を回す。
「リンタラ ランタラ ロリロリターン 紳士になぁれ!」
ネクタイピンから虹のような幻想的な光が放射され、
サオリの体がその光に包まれて消えていく。
次に姿を現せたとき、
サオリはすらりと背の高い紳士に変身していた・・・はずだった。
実は失敗して変身をし損ねたのだ。そんなことも知らずにサオリは、
それとばかりにクローゼットの中にある魔法のエレベーターに飛び乗った。
こちらの世界が夜であれば、あちらの世界も夜である。
遅くなっちゃった・・・もう気もそぞろで景色を見る余裕もない。
このエレベーターはガラス張りになっていて、
サオリはいつも外の美しい景色を見るのを楽しみにしているのだ。
「チンッ」と鳴ってエレベーターが止まる。
扉が開いてサオリは降りた。
コツコツコツと老婦人の急いだような足音が近づいて来る。
「あなた、今日は遅かったのね!」
期待に満ちた声をあげながら
ドレスの裾を両手で持って駆け寄る老婦人。
「ただい・・」と言いかけたサオリの声が止まる。
ゲッ、男の声じゃない・・・
「あら、お客様だったのね、お嬢さんどなた?」
老婦人はがっかりした気持ちを抑え、優しい顔で小首を傾げた。
(うへっ、しまったぁ、変身し損ねた ! )
* story *
サオリは何んにでも変身できる
ちょっと変わった高校二年生。
今日は部活のミーティングが長引いて、
窓の外はすっかり夜。それでもって壁の時計はもう6時。
「大変〜!またこんな時間になっちゃった。
もうっ、今日こそは、絶対おばあさんの所に行ってあげようと
思っているのにぃ・・・
でもでも、遅くなっても今日こそ行くぅ〜
今日こそ行ってあげないと可哀相だもん」
サオリはいつも一緒に帰る友達に、
急いでいるのゴメン!!と片手で詫びて走っていった。
夜道に並ぶ街灯を通り過ぎて数分、左手方向に
2階建てのサオリの家が見える。
玄関で脱いだ靴を跳ね飛ばし、
サオリは階段を駆け上がり自分の部屋に飛び込んだ。
魔法を使っているところを誰かに見られたら、
もう二度と魔法が使えなくなる。
慌ててカーテンを閉め、両親が留守なのを確認し、
例のネクタイピンをスカートのポケットの中から取り出した。
サオリは腕を伸ばし、
円を描く様にネクタイピンをつかんだ手を回す。
「リンタラ ランタラ ロリロリターン 紳士になぁれ!」
ネクタイピンから虹のような幻想的な光が放射され、
サオリの体がその光に包まれて消えていく。
次に姿を現せたとき、
サオリはすらりと背の高い紳士に変身していた・・・はずだった。
実は失敗して変身をし損ねたのだ。そんなことも知らずにサオリは、
それとばかりにクローゼットの中にある魔法のエレベーターに飛び乗った。
こちらの世界が夜であれば、あちらの世界も夜である。
遅くなっちゃった・・・もう気もそぞろで景色を見る余裕もない。
このエレベーターはガラス張りになっていて、
サオリはいつも外の美しい景色を見るのを楽しみにしているのだ。
「チンッ」と鳴ってエレベーターが止まる。
扉が開いてサオリは降りた。
コツコツコツと老婦人の急いだような足音が近づいて来る。
「あなた、今日は遅かったのね!」
期待に満ちた声をあげながら
ドレスの裾を両手で持って駆け寄る老婦人。
「ただい・・」と言いかけたサオリの声が止まる。
ゲッ、男の声じゃない・・・
「あら、お客様だったのね、お嬢さんどなた?」
老婦人はがっかりした気持ちを抑え、優しい顔で小首を傾げた。
(うへっ、しまったぁ、変身し損ねた ! )
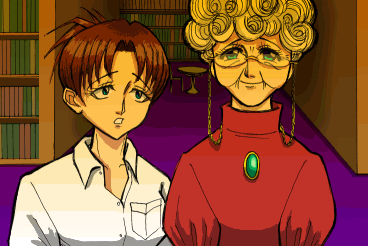 * story *
変身も出来ていないままの姿で城に現れてしまい、
サオリはどうしようかとうろたえるばかり。
「どなたかわからないけどちょうど寂しかったところなの。
ゆっくりしていってちょうだいね。
なんにもないけど、良かったらクッキーと紅茶を召し上がれ。
今日焼いたばかりなんだけど、お気に召すかしら」
老婦人がトレーにクッキーとポット、二人分のカップソーサーを乗せてやって来た。
「ありがとうございます」
サオリは何も思いつかないまま、とにかくクッキーに手を伸ばした。
「わぁ、美味しい!」
「うふふ、主人が帰ってきたときに出すつもりだったけど
今夜も帰れそうにないわ」
老婦人はフッと悲しい顔をみせた。
サオリもそれに気づき、とても切ない気持ちになる。
(本当はおばあさんのご主人になって来る筈だったのに、
おばあさんごめんなさい・・)
彼女は心の中で謝った。
「良かったら主人の写真を見てくださる?」
と言って老婦人はサオリにウィンクを投げかけた。
「え?いいのですか。ありがとうございます」
彼女の夫の部屋に行くといつものように天井にまで届くほど本が積みあがっている。
「びっくりしたでしょ、主人は本が大好きでね」
老婦人は言いながら壁に掛かった写真を指差す。
それは若い男と女がツーショットの古い写真。
* story *
変身も出来ていないままの姿で城に現れてしまい、
サオリはどうしようかとうろたえるばかり。
「どなたかわからないけどちょうど寂しかったところなの。
ゆっくりしていってちょうだいね。
なんにもないけど、良かったらクッキーと紅茶を召し上がれ。
今日焼いたばかりなんだけど、お気に召すかしら」
老婦人がトレーにクッキーとポット、二人分のカップソーサーを乗せてやって来た。
「ありがとうございます」
サオリは何も思いつかないまま、とにかくクッキーに手を伸ばした。
「わぁ、美味しい!」
「うふふ、主人が帰ってきたときに出すつもりだったけど
今夜も帰れそうにないわ」
老婦人はフッと悲しい顔をみせた。
サオリもそれに気づき、とても切ない気持ちになる。
(本当はおばあさんのご主人になって来る筈だったのに、
おばあさんごめんなさい・・)
彼女は心の中で謝った。
「良かったら主人の写真を見てくださる?」
と言って老婦人はサオリにウィンクを投げかけた。
「え?いいのですか。ありがとうございます」
彼女の夫の部屋に行くといつものように天井にまで届くほど本が積みあがっている。
「びっくりしたでしょ、主人は本が大好きでね」
老婦人は言いながら壁に掛かった写真を指差す。
それは若い男と女がツーショットの古い写真。
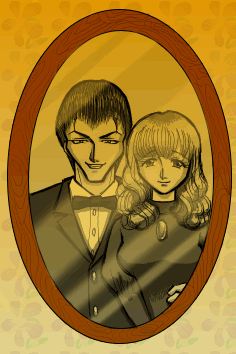 「これは若いときの私達・・・
もうこんなにお婆ちゃんになっちゃったわ」
「いえいえ、とんでもない!今でも十分お綺麗ですよ」
サオリは慌てて言った。
「おほほ、いいのよ。本当のことなんだから。
でもそう言ってもらえると嬉しいわ」
老婦人は懐かしそうに目を細め、
「この頃は最高に幸せだったわ。
主人はハンサムだったのでよく女の子達からモテていたの。
私も好きだったんだけど、とても近づけなくって、
遠くから見守っているしか出来なかったわ。
でもあるとき突然彼に告白されたの。
あのときは本当に驚いちゃって、夢かと思ったわ。
それから彼と結婚して、こうやって二人で暮らしているけど、
最近主人はお仕事が忙しくってなかなか帰ってこれないのよ」
老婦人は寂しげに目を伏せる。
サオリは切なくてたまらなくなっていた。
「これは若いときの私達・・・
もうこんなにお婆ちゃんになっちゃったわ」
「いえいえ、とんでもない!今でも十分お綺麗ですよ」
サオリは慌てて言った。
「おほほ、いいのよ。本当のことなんだから。
でもそう言ってもらえると嬉しいわ」
老婦人は懐かしそうに目を細め、
「この頃は最高に幸せだったわ。
主人はハンサムだったのでよく女の子達からモテていたの。
私も好きだったんだけど、とても近づけなくって、
遠くから見守っているしか出来なかったわ。
でもあるとき突然彼に告白されたの。
あのときは本当に驚いちゃって、夢かと思ったわ。
それから彼と結婚して、こうやって二人で暮らしているけど、
最近主人はお仕事が忙しくってなかなか帰ってこれないのよ」
老婦人は寂しげに目を伏せる。
サオリは切なくてたまらなくなっていた。
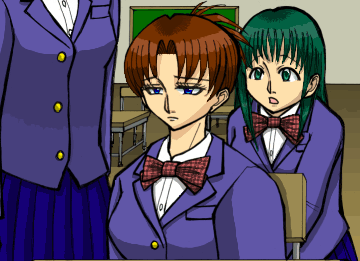 * story *
昨日からお婆さんのことが気になっているサオリ。
今日も朝からずっとどこか遠くを見ながら思いつめている。
一時間目の授業が終わり、友達がサオリの席までやって来た。
「昨日さぁ、ムッチャ笑えるテレビあったんだよぉー」
「へえー・・・・」
「私は学校帰りにコンビニに寄ってさあー
雑誌見てたら面白い記事が載っててぇー」
「フゥーン・・・・」
「うちの弟がまた覗き見しやがったんだけどぉー・・ん?
ねえっサオリったら! さっきから何ボケーッとしてんのよ」
話にサオリが乗ってこないので、友達が不満そうに言った。
「どないしたん、サオリ。今日は元気があらへんなぁ?」
と関西弁で声をかけてきたのは深緑色に髪の毛を染めたマナミだ。
他の皆もそれに同調して首を振る。
「え?そ、そうかな?全然そんなことないよー」
とサオリは何んでもないような顔をしてブンブンと手を振ったが、
取って付けたような笑いにいっそう怪しまれてしまう。
「怪しいなあ・・・何か私らに隠していることがあるみたいね」
別の友達が言った。
「いやっ、ホント何にもないよ。
ゴメンゴメンちょっと疲れてただけ」
「隠さずに言いなよ、相談に乗るからさあ」
「有難いけど本当に悩みなんてないの。
た、多分この頃早くお腹が空くから元気がなくなっちゃうのかなー」
タハハとサオリは頭をかきながら、男のような笑い方をした。
「もう、サオリったら心配させないで〜」
とマナミが両手で口を抑えながらクスクスと笑う。
皆と一緒に笑いながら、サオリは心の中でつぶやいた。
(この間のお婆さんは可哀相だったな・・)
* story *
昨日からお婆さんのことが気になっているサオリ。
今日も朝からずっとどこか遠くを見ながら思いつめている。
一時間目の授業が終わり、友達がサオリの席までやって来た。
「昨日さぁ、ムッチャ笑えるテレビあったんだよぉー」
「へえー・・・・」
「私は学校帰りにコンビニに寄ってさあー
雑誌見てたら面白い記事が載っててぇー」
「フゥーン・・・・」
「うちの弟がまた覗き見しやがったんだけどぉー・・ん?
ねえっサオリったら! さっきから何ボケーッとしてんのよ」
話にサオリが乗ってこないので、友達が不満そうに言った。
「どないしたん、サオリ。今日は元気があらへんなぁ?」
と関西弁で声をかけてきたのは深緑色に髪の毛を染めたマナミだ。
他の皆もそれに同調して首を振る。
「え?そ、そうかな?全然そんなことないよー」
とサオリは何んでもないような顔をしてブンブンと手を振ったが、
取って付けたような笑いにいっそう怪しまれてしまう。
「怪しいなあ・・・何か私らに隠していることがあるみたいね」
別の友達が言った。
「いやっ、ホント何にもないよ。
ゴメンゴメンちょっと疲れてただけ」
「隠さずに言いなよ、相談に乗るからさあ」
「有難いけど本当に悩みなんてないの。
た、多分この頃早くお腹が空くから元気がなくなっちゃうのかなー」
タハハとサオリは頭をかきながら、男のような笑い方をした。
「もう、サオリったら心配させないで〜」
とマナミが両手で口を抑えながらクスクスと笑う。
皆と一緒に笑いながら、サオリは心の中でつぶやいた。
(この間のお婆さんは可哀相だったな・・)
 * story *
「はぁ〜、皆に心配をさせちゃった・・・」
前かがみに歩きながら、サオリはため息ばかりつきまくっていた。
学校からの帰り道、サオリの首は
お辞儀をしたひまわりのようにしなだれたまま。
「まだ痛むなぁ・・おもいっきし直撃だモンねぇ」
鼻先が赤く腫れている。
体育のドッジボールのときに、ボーッと突っ立っていたサオリは
顔面にボールの直撃を受けた。
今日は一日中お婆さんのことで頭がいっぱいだったのだ。
今でもまだジンジン痛むが、お婆さんのことを思うと
鼻の痛みが胸の痛みに変っていく。
「あぁ〜、あたしってドジ・・・」
またため息を一つ漏らし、ようやく家の前。
ドアを開けたものの、誰とも会いたくない気分なので、
ソロリソロリと自分の部屋にすっこもうと思ったが
台所の辺りからパタパタ
スリッパの音がだんだんこちらに近付いてくる。
「お帰りっ」
満面笑顔で迎える母親が、エプロン姿でサオリの前に立った。
「ただいま・・」
たちまち気分が重くなる。
「マアッ! あんた鼻が腫れてるわよ」
目を皿のように丸くした母親は、どうしたの?とサオリに詰め寄った。
(うっっ、知られてしまったか・・・説明するのも鬱陶しい)
「あ、大丈夫。ちょっと体育の時間にボールがね」
「大丈夫なの?バンソウコウとか持ってこようか」
「・・いい」サオリは無理にニッと笑った。
「今日は散々だったみたいだけど、でも苦あれば楽ありと言うじゃない!
今晩のおかずは・・ジャジャーン、何とオムライスでーす」
ウインクしながら片手でピースサインをしている母親には申し訳ないと思ったけれど、
今日のサオリは食欲ゼロ状態。
「ごめん、お母さん・・今日はいらない」
サオリが大好きなオムライスをいらないと言った。
こんなことは初めてである。
母親は、大事な娘の一大事を察知した。
「サオリ、何か悩みがあるんじゃないの?お母さんに話して」
「あ・・・うん、全然平気。お腹がその・・・空いてないだけよ。
言うの忘れたけど、さっき友達とハンバーガー食べてきたの」
嘘をついたサオリは母親からの追求を逃れるように、
素早く階段を駆けあがっていった。
「それならいいんだけど、何かあったら本当にお母さんに言いなさいよ」
母親の心配そうな声を背中に聞きながら、
サオリはハ〜イと軽く返事して部屋のドアを閉めた。
「ごめんね、お母さん。お母さんにでも言えないことなの」
ドアにもたれてサオリはつぶやいた。
鞄を放り投げて仰向けにベッドに倒れこんだサオリは、
ちらっと横目で押入れを見る。
この押入れの中は未来へ通じるエレベータがあって、
上にあがるとお婆さんが住んでいる城に着くのだ。
「お婆さんの旦那さんは、変装をしている私なんだよね。
それって騙しているってことじゃん。
そんなのお婆さんが可哀想だよ。本物のお爺さんに会わせてあげたいけど、
どこにいるのか全くわかんないし・・・
あぁ、もうお婆さんに本当のことを言ったほうがいいのかな、
それともこのままお婆さんに夢を見させたほうがいいのかな。 どうしよう・・」
サオリが額に手を当ててぶつぶつ独り言を言っているときドアが細く開けられた。
* story *
「はぁ〜、皆に心配をさせちゃった・・・」
前かがみに歩きながら、サオリはため息ばかりつきまくっていた。
学校からの帰り道、サオリの首は
お辞儀をしたひまわりのようにしなだれたまま。
「まだ痛むなぁ・・おもいっきし直撃だモンねぇ」
鼻先が赤く腫れている。
体育のドッジボールのときに、ボーッと突っ立っていたサオリは
顔面にボールの直撃を受けた。
今日は一日中お婆さんのことで頭がいっぱいだったのだ。
今でもまだジンジン痛むが、お婆さんのことを思うと
鼻の痛みが胸の痛みに変っていく。
「あぁ〜、あたしってドジ・・・」
またため息を一つ漏らし、ようやく家の前。
ドアを開けたものの、誰とも会いたくない気分なので、
ソロリソロリと自分の部屋にすっこもうと思ったが
台所の辺りからパタパタ
スリッパの音がだんだんこちらに近付いてくる。
「お帰りっ」
満面笑顔で迎える母親が、エプロン姿でサオリの前に立った。
「ただいま・・」
たちまち気分が重くなる。
「マアッ! あんた鼻が腫れてるわよ」
目を皿のように丸くした母親は、どうしたの?とサオリに詰め寄った。
(うっっ、知られてしまったか・・・説明するのも鬱陶しい)
「あ、大丈夫。ちょっと体育の時間にボールがね」
「大丈夫なの?バンソウコウとか持ってこようか」
「・・いい」サオリは無理にニッと笑った。
「今日は散々だったみたいだけど、でも苦あれば楽ありと言うじゃない!
今晩のおかずは・・ジャジャーン、何とオムライスでーす」
ウインクしながら片手でピースサインをしている母親には申し訳ないと思ったけれど、
今日のサオリは食欲ゼロ状態。
「ごめん、お母さん・・今日はいらない」
サオリが大好きなオムライスをいらないと言った。
こんなことは初めてである。
母親は、大事な娘の一大事を察知した。
「サオリ、何か悩みがあるんじゃないの?お母さんに話して」
「あ・・・うん、全然平気。お腹がその・・・空いてないだけよ。
言うの忘れたけど、さっき友達とハンバーガー食べてきたの」
嘘をついたサオリは母親からの追求を逃れるように、
素早く階段を駆けあがっていった。
「それならいいんだけど、何かあったら本当にお母さんに言いなさいよ」
母親の心配そうな声を背中に聞きながら、
サオリはハ〜イと軽く返事して部屋のドアを閉めた。
「ごめんね、お母さん。お母さんにでも言えないことなの」
ドアにもたれてサオリはつぶやいた。
鞄を放り投げて仰向けにベッドに倒れこんだサオリは、
ちらっと横目で押入れを見る。
この押入れの中は未来へ通じるエレベータがあって、
上にあがるとお婆さんが住んでいる城に着くのだ。
「お婆さんの旦那さんは、変装をしている私なんだよね。
それって騙しているってことじゃん。
そんなのお婆さんが可哀想だよ。本物のお爺さんに会わせてあげたいけど、
どこにいるのか全くわかんないし・・・
あぁ、もうお婆さんに本当のことを言ったほうがいいのかな、
それともこのままお婆さんに夢を見させたほうがいいのかな。 どうしよう・・」
サオリが額に手を当ててぶつぶつ独り言を言っているときドアが細く開けられた。
 * story *
ドアがゆっくりと開くのがわかった。
見慣れたジーパンを履いた足がチラッと見えた瞬間、
サオリはわざと体をねじらせて、枕に顔を埋めた。
「ごめんね、勝手に入っちゃって。
ノックをしてもあんたの返事が全然なくて、心配になったのよ」
母がそっと近づいてくるのがわかる。
「・・なんか用?」
サオリは枕に顔を埋めたまま、ぶっきらぼうな声をだした。
母は娘から何があったかを聞きたかったが、いきなり聞いても、
また何もないと娘に言われてしまうと思ったらしく、おずおずと
「サオリ、ちょっとだけ私の話を聞いてくれる?」と聞いてきた。
しばらくサオリは固まったまま黙っていたが、
数回枕にグイグイと頭を押し付ける仕草をした。
それがサオリの いいよという返事だと受け取った母は、
ゆっくりとサオリの横に腰をおろした。
それでもサオリはまだ動かない。
顔も枕に埋めたままだ。
「サオリに何かあると、お母さんには分かるのよ」
サオリには頭上から温かい母の声が降りそそぐように感じた。
サオリは本当は母に聞いてほしかった。
でも、話したところで信じてはもらえない・・・
だから、ずっと我慢していたのだ。
「私は、あんたのお母さんだからね。いつも頭の中はあんたと繋がっているの。
だからあんたが一大事のときはビビッと感じるのよ」
母の言葉は神様の温かい慈悲のようにサオリの心にしみた。
サオリは、モゾモゾと体を起こして母の隣に座った。
やっと娘が心を開いてくれたみたいなので、母はホッとして微笑む。
「話したくなかったら何も言わなくてもかまわないのよ。
でも、お母さんに話してちょっとでも気持ちが軽くなるのなら、
話してちょうだい。おかあさんはサオリの暗い顔を見るのが辛いのよ。
いつも明るいあんたが、元気がないということが心配なの。食欲もないだなんて・・・
オムライスはあんたの大好物なのにね」
サオリは自分が母にとって、分かりやすい性格だと知り、少し恥ずかしくなった。
「何があったのか話してみない?一人で悩んでいるよりは、
ずっと楽なんじゃないかなってお母さん思うのよ。」
サオリは、母の優しい言葉に驚きとともに大きな親の愛を感じた。
思わず悩みを全部打ち明けたくなる衝動にかられたが、
サオリの悩みは普通に考えると到底信じてもらえる話しではないので、
ここは少し工夫をしてなるべく現実らしく言ってみようと考えた。
「あのね・・・聞いてくれる?」
口を開けるということが、こんなにも重労働なのかとサオリは感じる。
「ええ、いいわよ。話して」
母はニッコリと微笑んだ。
「あたしの知り合いに、お婆さんがいるの。
そのお婆さんは一人ぼっちで暮らしていて、
戦争で亡くなったお爺さんをずっと待っているの。
私がお婆さんの家で話をしているときに、
いきなり、あなた帰って来たの?と信じられないことをお婆さんが言い出して、
それからずっとあたしのことをお爺さんだと思い込んでいるの。
可哀相だから、学校帰りとかに時々お婆さんの家に寄っているけど、
ずっとあたしのことをお爺さんだと思って待っているの。
お婆さんは89歳でお年寄りだし、
あたしがお爺さんじゃないって言ったらショックで死んでしまうんじゃないかと思う。
でも、お婆さんの私を見る嬉しそうな顔が辛くって・・・・
だって、こんなのみんな幻覚だものね。
私はお婆さんの旦那さんじゃないもの。
私はどうすればいいのかな・・・
お婆さんにとっての幸せって何なんだろうって考えたら、
このままずっとお爺さんになりきるしかないんだろうけど・・・。
私も辛いのよ」
母は最初ビックリしたような顔をしたが、やがてまた優しく微笑んだ。
「サオリがそんなことをしていただなんて、とても驚いたけど、
サオリはとってもいいことをしているとお母さんは思うわ。
でも、案外お婆さんは何もかも承知の上なのかもよ。
お婆さんはサオリのことを気に入ったからお爺さんだと思い込みたいだけなのかもしれないわ。
お婆さんは一人ぼっちで寂しいのよ。
きっとサオリにお爺さんの姿をだぶらせて、淋しさを紛らわせているんだわ。
サオリもそんなふうに考えて、お婆さんに接してあげればどうかな。
現実を突きつけるような惨いことだけはしてほしくないわね」
サオリは深くうなづく。
たしかに、自分の変身している姿形は紳士そのものだが、
話をすると年齢がバレるはず。
きっとお婆さんはサオリがお爺さんではないことを、
もう気づいているかもしれないなとサオリは思った。
「だから、本当のことなんて言わなくていいんじゃないかな。
サオリと過ごす時間がお婆さんにとって幸せなひと時なのよ」
母がにっこりと微笑んだのでつられてサオリも笑った。
「そうかぁ・・・そういわれてみればそうだよね。
私がお爺さんじゃないってことは、お婆さんにはもうわかっているよね」
「そうそう、だからこれから先もお婆さんの話し相手になってあげなさい。
けど、あんたにはそういう優しいところがあったんだ・・・お母さん、感心しちゃった」
母はスペシャルスマイルをサオリに投げ掛ける。
「うん、わかった。お母さんありがとう。
なんか、とても気持が楽になったよ」
縁もゆかりも無い孤独な老女を思いやる、
優しい娘に育ってくれたことが、母にとってはとても嬉しいことだった。
「いえいえ。あっ、お腹が空いたでしょ。
実はお母さんもまだ食べてなかったの。一緒にオムライス食べようよ」
「わーい!食べよう食べよう」
ぐぅ〜・・・。
大きな腹の虫の鳴き声が聞こえて、思わずサオリは赤面してお腹を抱える。
「あら!大きな音」
母があはは!とサオリのお腹に指を指して笑い、サオリもいやだぁ〜といって照れ笑いをする。
母と娘の笑い声が部屋の中に満ち溢れた。
* story *
ドアがゆっくりと開くのがわかった。
見慣れたジーパンを履いた足がチラッと見えた瞬間、
サオリはわざと体をねじらせて、枕に顔を埋めた。
「ごめんね、勝手に入っちゃって。
ノックをしてもあんたの返事が全然なくて、心配になったのよ」
母がそっと近づいてくるのがわかる。
「・・なんか用?」
サオリは枕に顔を埋めたまま、ぶっきらぼうな声をだした。
母は娘から何があったかを聞きたかったが、いきなり聞いても、
また何もないと娘に言われてしまうと思ったらしく、おずおずと
「サオリ、ちょっとだけ私の話を聞いてくれる?」と聞いてきた。
しばらくサオリは固まったまま黙っていたが、
数回枕にグイグイと頭を押し付ける仕草をした。
それがサオリの いいよという返事だと受け取った母は、
ゆっくりとサオリの横に腰をおろした。
それでもサオリはまだ動かない。
顔も枕に埋めたままだ。
「サオリに何かあると、お母さんには分かるのよ」
サオリには頭上から温かい母の声が降りそそぐように感じた。
サオリは本当は母に聞いてほしかった。
でも、話したところで信じてはもらえない・・・
だから、ずっと我慢していたのだ。
「私は、あんたのお母さんだからね。いつも頭の中はあんたと繋がっているの。
だからあんたが一大事のときはビビッと感じるのよ」
母の言葉は神様の温かい慈悲のようにサオリの心にしみた。
サオリは、モゾモゾと体を起こして母の隣に座った。
やっと娘が心を開いてくれたみたいなので、母はホッとして微笑む。
「話したくなかったら何も言わなくてもかまわないのよ。
でも、お母さんに話してちょっとでも気持ちが軽くなるのなら、
話してちょうだい。おかあさんはサオリの暗い顔を見るのが辛いのよ。
いつも明るいあんたが、元気がないということが心配なの。食欲もないだなんて・・・
オムライスはあんたの大好物なのにね」
サオリは自分が母にとって、分かりやすい性格だと知り、少し恥ずかしくなった。
「何があったのか話してみない?一人で悩んでいるよりは、
ずっと楽なんじゃないかなってお母さん思うのよ。」
サオリは、母の優しい言葉に驚きとともに大きな親の愛を感じた。
思わず悩みを全部打ち明けたくなる衝動にかられたが、
サオリの悩みは普通に考えると到底信じてもらえる話しではないので、
ここは少し工夫をしてなるべく現実らしく言ってみようと考えた。
「あのね・・・聞いてくれる?」
口を開けるということが、こんなにも重労働なのかとサオリは感じる。
「ええ、いいわよ。話して」
母はニッコリと微笑んだ。
「あたしの知り合いに、お婆さんがいるの。
そのお婆さんは一人ぼっちで暮らしていて、
戦争で亡くなったお爺さんをずっと待っているの。
私がお婆さんの家で話をしているときに、
いきなり、あなた帰って来たの?と信じられないことをお婆さんが言い出して、
それからずっとあたしのことをお爺さんだと思い込んでいるの。
可哀相だから、学校帰りとかに時々お婆さんの家に寄っているけど、
ずっとあたしのことをお爺さんだと思って待っているの。
お婆さんは89歳でお年寄りだし、
あたしがお爺さんじゃないって言ったらショックで死んでしまうんじゃないかと思う。
でも、お婆さんの私を見る嬉しそうな顔が辛くって・・・・
だって、こんなのみんな幻覚だものね。
私はお婆さんの旦那さんじゃないもの。
私はどうすればいいのかな・・・
お婆さんにとっての幸せって何なんだろうって考えたら、
このままずっとお爺さんになりきるしかないんだろうけど・・・。
私も辛いのよ」
母は最初ビックリしたような顔をしたが、やがてまた優しく微笑んだ。
「サオリがそんなことをしていただなんて、とても驚いたけど、
サオリはとってもいいことをしているとお母さんは思うわ。
でも、案外お婆さんは何もかも承知の上なのかもよ。
お婆さんはサオリのことを気に入ったからお爺さんだと思い込みたいだけなのかもしれないわ。
お婆さんは一人ぼっちで寂しいのよ。
きっとサオリにお爺さんの姿をだぶらせて、淋しさを紛らわせているんだわ。
サオリもそんなふうに考えて、お婆さんに接してあげればどうかな。
現実を突きつけるような惨いことだけはしてほしくないわね」
サオリは深くうなづく。
たしかに、自分の変身している姿形は紳士そのものだが、
話をすると年齢がバレるはず。
きっとお婆さんはサオリがお爺さんではないことを、
もう気づいているかもしれないなとサオリは思った。
「だから、本当のことなんて言わなくていいんじゃないかな。
サオリと過ごす時間がお婆さんにとって幸せなひと時なのよ」
母がにっこりと微笑んだのでつられてサオリも笑った。
「そうかぁ・・・そういわれてみればそうだよね。
私がお爺さんじゃないってことは、お婆さんにはもうわかっているよね」
「そうそう、だからこれから先もお婆さんの話し相手になってあげなさい。
けど、あんたにはそういう優しいところがあったんだ・・・お母さん、感心しちゃった」
母はスペシャルスマイルをサオリに投げ掛ける。
「うん、わかった。お母さんありがとう。
なんか、とても気持が楽になったよ」
縁もゆかりも無い孤独な老女を思いやる、
優しい娘に育ってくれたことが、母にとってはとても嬉しいことだった。
「いえいえ。あっ、お腹が空いたでしょ。
実はお母さんもまだ食べてなかったの。一緒にオムライス食べようよ」
「わーい!食べよう食べよう」
ぐぅ〜・・・。
大きな腹の虫の鳴き声が聞こえて、思わずサオリは赤面してお腹を抱える。
「あら!大きな音」
母があはは!とサオリのお腹に指を指して笑い、サオリもいやだぁ〜といって照れ笑いをする。
母と娘の笑い声が部屋の中に満ち溢れた。
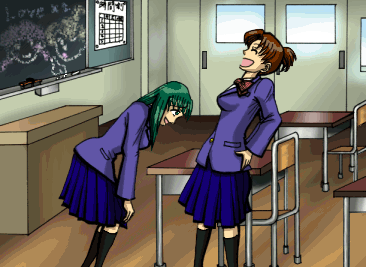 * story *
昨夜、母に相談をして安心しきったサオリはぐっすりと眠ってしまった。
ベッドの上で寝ていたサオリはゆっくりと目を開ける。
小鳥のさえずりとカーテンの隙間からこぼれる日差しが穏やかな朝を迎えたが、それも束の間。
一瞬不安が過ぎった彼女はおそるおそる、枕もとの時計を見遣る。
予想通り、サオリは目覚ましの鳴る音に気がつかず遅刻をしてしまった。
「いっけね、また遅刻だよ〜!」
遅刻をするのは稀ではなかったらしい。
慌ててベッドから飛び上がるように起きたサオリは、
真っ先に机の上に置いてあった鞄を床に引きずり下ろす。
机の上でも学校の用意はできないことないが、
こういう時間の余裕がないときは何の障害物もない広いところでしたいものだ。
当日になって学校にいく準備をする彼女は、慌てて今日の分の教科書を鞄の中に押し込んだ。
早回しのように髪を乱暴にブラシでといてセットし、
洗面台の周りがびしょびしょになるのをお構いなしに顔を洗う。
パジャマを脱いで制服を無造作に着る。
仕上げに片足でぴょんぴょん飛び跳ねながら靴下を履いた。
鞄をもったサオリはパタパタと忙しく階段を降りる。
「遅かったわね、今日休みだったっけ」
リビングに入ると、母が机の上のスーパーやダイエット関係のチラシを見て寛いでいた。
「違うよ、遅刻遅刻!朝ご飯作ってくれてないの?もうこのまんま行くからね、時間ないし」
早口で捲くし立て、家から出て行こうとしたサオリを止めるように言った。
「ちょいお待ち、朝ご飯はここにあるでしょ。見えてなかったの」
ちょいちょいと指さすところを見ると、
沢山のチラシの前に目玉焼きトーストと牛乳が置いてあった。
急いでいたものだから、あることに気がつかなかったのである。
「そんなに急いでいるのなら口に銜えて行きなさい、ほれ」
母は娘に目玉焼きトーストを銜えさせる。
食べ盛りの娘を思って、わざわざトーストのみではなく目玉焼きつきのトーストにした。
「サンキュ、行って来まーす!」
スカートを翻し、リビングから出て廊下を走ろうとしたときにサオリは滑りかけた。
危なっかしくて見ていられなくなった母は椅子から
よっこらしょっと立ち上がりついて行こうとする。
「気をつけていくのよ、あせらずに」
「うん、わかった〜!んじゃ」
と言いながら廊下を走り抜けたサオリは玄関のドアを開けて行った。
母は玄関から外に出て見送ろうとしたが、
遠くまでいってしまった娘を見てため息をついた。
「あんなに走っちゃ事故を起こしかねないよ、まったく・・」
もう少し鳴る音が分かる目覚まし時計を買ってあげようかなぁ〜・・
と言いながら中に入った。
息切れをしながらもようやく門までたどり着いたサオリは、
ギリギリで予鈴に間に合った。
しかし本鈴まであと10分しかないので最後の力を振り絞って階段を駆け上がる。
一気に5階まで上がりきって、へとへとになってしまった。
ふらふらになりつつもサオリは考えつく、
2時間目の体育の時間で使う体力は残っていないかも・・と。
やっと教室の前までつき、
ぜーぜー言いながらドアのもち手をがしっと掴んでゆっくりと開ける。
授業が始まるまであと5分しかないのに
まだクラスの全員は雑談をしたりトランプなどで遊んだりしていた。
「おはよう!」
幼馴染のマナミが駆け寄った。この子は大阪出身なので、関西弁で話すのだ。
「はぁ・・はぁ、おはよう。なんとか、本鈴までに間に合ったよ」
「お疲れさん、あんたも朝から大変やね〜。こうも遅刻が続いてたらある意味鍛えられるかもなぁ」
「本当だね、でもこんな形で鍛え上げられるのはありがた迷惑だよ・・」
キーンコーンカーンコーン・・・
チャイムが鳴ると同時に木下先生が入ってきた。
この先生は時間にはうるさく、遅刻すると容赦ないのだ。
偶然かどうかわからないがいつもチャイムと同時にやってくる。
そういえば一時間目は数学だったっけ。
自分の席に向かって座り、鞄の中から数学の教科書を出して準備をした。
サオリは数学が苦手なので、
毎回ばれないようにらくがきをしたり寝たりしてやり過ごしている。
しかし、他の事をして気を紛らわす必要はなかった。
今日に限って授業が退屈ではなく苦痛も感じない。
昨夜、母に相談したお陰だろうかなんだかモヤモヤが薄れて心が軽くなった気分だ。
この授業は最後までノートをしっかりとり問題も解こうという姿勢を見せて授業を受けた、
おおよそ半分も授業の理解をしていなかったが。
授業が終わり、10分間の休憩に入った。
朝ギリギリに入ってマナミとは十分に話せなかったので、
マナミの席のところまで自分から行こうとしたが、
こっちにマナミがやってくることに気づき、一度上げかけた腰を下ろした。
「今日はサオリの嫌いな数学の授業なのに、最後まで真面目に受けてたやん。感心感心〜」
幼馴染なのでサオリの好きな物から嫌いな物まで知り尽くしている。
兄弟を見るように本当に感心をしている様子だった。
「なんか今日ぐらいは受けようと思ったのよ、このまんまじゃぁ数学が嫌いなまんまだしさ」
「ほほぉ〜、いつのまにかサオリは成長しましたなぁ」
背中に手を組んで聞いているマナミ。
「・・それにあの先生の授業は退屈だからみんな話を聞いてないじゃん?
私だけでも聞いてあげないと可愛そうだと思ってね」
ニヒ〜と歯をむき出して悪戯っぽく笑った。
「あややぁ〜、せっかく見直したというのになんか落胆したわぁ」
オーバーに体が崩れるようにがっかりするマナミを見てサオリは大笑いをした。
「ところでサオリ、昨日は大丈夫やった?」
へらへら笑っていたマナミがいきなり表情が硬くなった。
それが突然だったもので、一瞬言葉が詰まった。
「へ?うん、大丈夫だよ。なんだか変な心配をかけさせちゃったみたいだね。ごめん」
やり場がないので無意識にこめかみをぽりぽりと掻いてしまう。
「ううん、でも、このままずっと落ち込んでいたらサオリの相談に乗るつもりやってんよ。
うちはほんまに、あんたのことが心配やってん」
「マナミ・・・」
マナミとは幼稚園の頃からの付き合いだが、
こんなに自分のことが思われていたことがとても嬉しかった。
「けど、元のサオリに戻ったみたいで良かった〜。毎日の楽しい学校がまた始まるわ」
ニコっとマナミが微笑んだ。窓からの光が丁度マナミに射していたので笑顔が眩しく見えた。
「ありがとう。誰よりもマナミが一番友達だよ」
この子とは一生友達でいられるという直感がした。
「でもぉ〜どうしてそないに元気になったん?」
「え〜、何で?」
「何でって、気になるから聞くやんかぁ。おしえてーな」
マナミが膨れた顔をしてブーブー言っている。
いくら友達でも、
お婆さんのことや変身していることを言えないから適当な言葉を選ぶように考えた。
それからやっと出てきた言葉は
「オムライス」
「へっ?」
「昨夜、お母さんが作ってくれたオムライスのおかげだよ」
イェーイと言ってV(ヴイ)サインを見せる。
一瞬目が点になったマナミは、呆れた顔をして
「なぁんや、サオリらしい。心配して損したわぁ」と言った。
「なっなによ!オムライスは大好物だから仕方が無いじゃない」
「そうやけどぉ〜」
そうこうやり取りをしている内に休み時間が過ぎて2時間目の授業に移った。
サオリは授業を受けている間、ふとお婆さんのことが頭に過ぎった。
悩みも丁度ふっとんだところなのでサオリは決心をする。
“今日家に帰ったらお婆さんに会いに行こう!”
誰も聞こえないように小声で言った。
* story *
昨夜、母に相談をして安心しきったサオリはぐっすりと眠ってしまった。
ベッドの上で寝ていたサオリはゆっくりと目を開ける。
小鳥のさえずりとカーテンの隙間からこぼれる日差しが穏やかな朝を迎えたが、それも束の間。
一瞬不安が過ぎった彼女はおそるおそる、枕もとの時計を見遣る。
予想通り、サオリは目覚ましの鳴る音に気がつかず遅刻をしてしまった。
「いっけね、また遅刻だよ〜!」
遅刻をするのは稀ではなかったらしい。
慌ててベッドから飛び上がるように起きたサオリは、
真っ先に机の上に置いてあった鞄を床に引きずり下ろす。
机の上でも学校の用意はできないことないが、
こういう時間の余裕がないときは何の障害物もない広いところでしたいものだ。
当日になって学校にいく準備をする彼女は、慌てて今日の分の教科書を鞄の中に押し込んだ。
早回しのように髪を乱暴にブラシでといてセットし、
洗面台の周りがびしょびしょになるのをお構いなしに顔を洗う。
パジャマを脱いで制服を無造作に着る。
仕上げに片足でぴょんぴょん飛び跳ねながら靴下を履いた。
鞄をもったサオリはパタパタと忙しく階段を降りる。
「遅かったわね、今日休みだったっけ」
リビングに入ると、母が机の上のスーパーやダイエット関係のチラシを見て寛いでいた。
「違うよ、遅刻遅刻!朝ご飯作ってくれてないの?もうこのまんま行くからね、時間ないし」
早口で捲くし立て、家から出て行こうとしたサオリを止めるように言った。
「ちょいお待ち、朝ご飯はここにあるでしょ。見えてなかったの」
ちょいちょいと指さすところを見ると、
沢山のチラシの前に目玉焼きトーストと牛乳が置いてあった。
急いでいたものだから、あることに気がつかなかったのである。
「そんなに急いでいるのなら口に銜えて行きなさい、ほれ」
母は娘に目玉焼きトーストを銜えさせる。
食べ盛りの娘を思って、わざわざトーストのみではなく目玉焼きつきのトーストにした。
「サンキュ、行って来まーす!」
スカートを翻し、リビングから出て廊下を走ろうとしたときにサオリは滑りかけた。
危なっかしくて見ていられなくなった母は椅子から
よっこらしょっと立ち上がりついて行こうとする。
「気をつけていくのよ、あせらずに」
「うん、わかった〜!んじゃ」
と言いながら廊下を走り抜けたサオリは玄関のドアを開けて行った。
母は玄関から外に出て見送ろうとしたが、
遠くまでいってしまった娘を見てため息をついた。
「あんなに走っちゃ事故を起こしかねないよ、まったく・・」
もう少し鳴る音が分かる目覚まし時計を買ってあげようかなぁ〜・・
と言いながら中に入った。
息切れをしながらもようやく門までたどり着いたサオリは、
ギリギリで予鈴に間に合った。
しかし本鈴まであと10分しかないので最後の力を振り絞って階段を駆け上がる。
一気に5階まで上がりきって、へとへとになってしまった。
ふらふらになりつつもサオリは考えつく、
2時間目の体育の時間で使う体力は残っていないかも・・と。
やっと教室の前までつき、
ぜーぜー言いながらドアのもち手をがしっと掴んでゆっくりと開ける。
授業が始まるまであと5分しかないのに
まだクラスの全員は雑談をしたりトランプなどで遊んだりしていた。
「おはよう!」
幼馴染のマナミが駆け寄った。この子は大阪出身なので、関西弁で話すのだ。
「はぁ・・はぁ、おはよう。なんとか、本鈴までに間に合ったよ」
「お疲れさん、あんたも朝から大変やね〜。こうも遅刻が続いてたらある意味鍛えられるかもなぁ」
「本当だね、でもこんな形で鍛え上げられるのはありがた迷惑だよ・・」
キーンコーンカーンコーン・・・
チャイムが鳴ると同時に木下先生が入ってきた。
この先生は時間にはうるさく、遅刻すると容赦ないのだ。
偶然かどうかわからないがいつもチャイムと同時にやってくる。
そういえば一時間目は数学だったっけ。
自分の席に向かって座り、鞄の中から数学の教科書を出して準備をした。
サオリは数学が苦手なので、
毎回ばれないようにらくがきをしたり寝たりしてやり過ごしている。
しかし、他の事をして気を紛らわす必要はなかった。
今日に限って授業が退屈ではなく苦痛も感じない。
昨夜、母に相談したお陰だろうかなんだかモヤモヤが薄れて心が軽くなった気分だ。
この授業は最後までノートをしっかりとり問題も解こうという姿勢を見せて授業を受けた、
おおよそ半分も授業の理解をしていなかったが。
授業が終わり、10分間の休憩に入った。
朝ギリギリに入ってマナミとは十分に話せなかったので、
マナミの席のところまで自分から行こうとしたが、
こっちにマナミがやってくることに気づき、一度上げかけた腰を下ろした。
「今日はサオリの嫌いな数学の授業なのに、最後まで真面目に受けてたやん。感心感心〜」
幼馴染なのでサオリの好きな物から嫌いな物まで知り尽くしている。
兄弟を見るように本当に感心をしている様子だった。
「なんか今日ぐらいは受けようと思ったのよ、このまんまじゃぁ数学が嫌いなまんまだしさ」
「ほほぉ〜、いつのまにかサオリは成長しましたなぁ」
背中に手を組んで聞いているマナミ。
「・・それにあの先生の授業は退屈だからみんな話を聞いてないじゃん?
私だけでも聞いてあげないと可愛そうだと思ってね」
ニヒ〜と歯をむき出して悪戯っぽく笑った。
「あややぁ〜、せっかく見直したというのになんか落胆したわぁ」
オーバーに体が崩れるようにがっかりするマナミを見てサオリは大笑いをした。
「ところでサオリ、昨日は大丈夫やった?」
へらへら笑っていたマナミがいきなり表情が硬くなった。
それが突然だったもので、一瞬言葉が詰まった。
「へ?うん、大丈夫だよ。なんだか変な心配をかけさせちゃったみたいだね。ごめん」
やり場がないので無意識にこめかみをぽりぽりと掻いてしまう。
「ううん、でも、このままずっと落ち込んでいたらサオリの相談に乗るつもりやってんよ。
うちはほんまに、あんたのことが心配やってん」
「マナミ・・・」
マナミとは幼稚園の頃からの付き合いだが、
こんなに自分のことが思われていたことがとても嬉しかった。
「けど、元のサオリに戻ったみたいで良かった〜。毎日の楽しい学校がまた始まるわ」
ニコっとマナミが微笑んだ。窓からの光が丁度マナミに射していたので笑顔が眩しく見えた。
「ありがとう。誰よりもマナミが一番友達だよ」
この子とは一生友達でいられるという直感がした。
「でもぉ〜どうしてそないに元気になったん?」
「え〜、何で?」
「何でって、気になるから聞くやんかぁ。おしえてーな」
マナミが膨れた顔をしてブーブー言っている。
いくら友達でも、
お婆さんのことや変身していることを言えないから適当な言葉を選ぶように考えた。
それからやっと出てきた言葉は
「オムライス」
「へっ?」
「昨夜、お母さんが作ってくれたオムライスのおかげだよ」
イェーイと言ってV(ヴイ)サインを見せる。
一瞬目が点になったマナミは、呆れた顔をして
「なぁんや、サオリらしい。心配して損したわぁ」と言った。
「なっなによ!オムライスは大好物だから仕方が無いじゃない」
「そうやけどぉ〜」
そうこうやり取りをしている内に休み時間が過ぎて2時間目の授業に移った。
サオリは授業を受けている間、ふとお婆さんのことが頭に過ぎった。
悩みも丁度ふっとんだところなのでサオリは決心をする。
“今日家に帰ったらお婆さんに会いに行こう!”
誰も聞こえないように小声で言った。
 * story *
こくりこくりと寝ているときもあったが後ろに座っている友達が起こしてくれたので、
なんとか最後まで授業の話を聞くことができた。
授業終了後のHRが終わると、ん〜と言ってサオリは腕をいっぱいいっぱいに伸ばした。
「はぁ、終わった、終わったぁ!」
担任の先生が教室から出ていったあと、すぐに他の生徒達が立ち上がり教室が騒がしくなった。
生徒達のすることはまちまちで、黙々と帰りの支度をしたり一箇所に固まって雑談をしたり
ファーストフードやカラオケに誘ったりしている。
「いやぁ〜、先生の話を聞いてると勉強が分かりやすいなぁ。
明日もサボらずに授業をうけようっかな」
勉強の苦手だったサオリは、ようやく勉強をするコツを掴むことができた。
試験の直前なんかに勉強をするよりも、
日頃まじめに授業の話を聞いている方が負担もなく効率的に良いのだ。
「こんなことだったらもっと早くから気づけば良かったな!
徹夜までしていた自分が馬鹿らしいと思うよぉ〜」
今まで自分のしてきた要領の悪さを、腕を組みもって噛み締める。
「サオリぃ、早くしないとおいていくよー」
はっ、と気づいたときに、マナミ達は教室のドアの前から呼んでいた。
いつのまにか3人とも早くから帰る用意をして待っているみたいだった。
「えっ、あっ?ちょ、ちょっと待ってぇ〜。もう、早いんだよぉみんな!」
慌てて机の上に出した教科書やシャープペンシルをそのまま鞄にしまいこみ、
マナミ達のいるところまで小走りした。
友達と帰り道で別れたあと、駆け足で自宅に向かった。
「ただいま!」
玄関で脱いだ靴を跳ね飛ばしていきそうになったが、
何かを思い出したのかサオリは踵を返す。
いつもお母さんに注意されていることだからそろそろ直していかないとねっ、
と言って転がった靴を揃えた。
「おかえりなさい。今日は早くに帰れたのね」
さっきまでテレビを見て寛いでいた母は、リビングから出てくる。
母が玄関前までついたときに、綺麗に揃っている靴を見て驚いた。
「あら、いつもは靴を脱ぎ散らかしていくのに今日のあんたは偉いわねぇ」
うんうんと軽く頷いて感心をしていた。
「えっへん、日頃の自分は怠っているという事に気づいてね、
今日から改めようとおもってたのよ」
すごいでしょっ、と言って腰に手を当てる。
「いいことじゃない。それが長続きすればもっといいのにね〜」
うっ・・・図星だ。母はサオリの性格を知り尽くしている。
「こう見えても私は継続型だよ。私はするまでが遅いけど、
腰を上げるとハイパーになるんだから」
母は娘をからかって楽しんでいた。
「じゃあわたし、これから部屋で勉強をするから」
「ええ、わかったわ。今度の通知表の成績が上がっていたら、
お祝いをしてあげましょうかね」
「わぉ、お祝いお祝い!わたし、回転寿司にいきたいなぁ」
いいよと言ってくれることを期待するサオリは、母の周りでスキップをする。
「いいわ、その分たっぷりと勉強をするのよ」
「ハァーイ」
サオリはルンルン気分で階段を駆け上がり部屋にいった。
変身しているところを誰かに見られてはまずいので、
急いでカーテンを閉めドアに鍵をかける。
ごそっと、机の引き出しの中からネクタイピンを取り出す。
このネクタイピンは父のいらなくなったものであり、
魔法使いはこれに魔法をかけて変身できる道具にしたのだ。
ピンは外に出されて鈍い光を放っている。
「今日はお婆さんのところにいけるわ。待っててね、お婆さん」
ずっと孤独に自分を待ち続ける老婆の姿を思い浮かべてピンを翳した。
「メルトンジェ・ザトゥー・ムーフォス・ラントイア!」
どこの国の言葉か分からない魔法の言葉を唱えると、
ピンから強い光が放射されサオリの体がその光に包まれる。
自分の部屋だとは思えない光景になり、
周りの光の粒子が走っているように見えた。
いつのまにかサオリは浮いており、見下ろすと粒子が底から湧き上がっている。
強い風が吹かれているが、温かくて優しく包んでくれるような心地よいものがあった。
サオリの若々しい姿が徐々に皺が増え、ほどよく老け込む。
膨よかな女性らしい体つきが、
脂肪が減りうっすらと骨がみえるくらいゴツゴツとした体つきになった。
小柄な少女の肩が広くなり、身長が伸びて男らしい体になる。
白無地のシャツ、スラックス、蝶タイ、サスペンダー、背広などの正礼装を身にまとって
シルクハットを被ったあと、最後にステッキと手袋を身につけた。
徐々に湧き上がっていた光が薄くなっていき、変身が終わったことが分かる。
ベッドの傍にあるクローゼットを開け、扉の後ろについてある全身鏡で確かめた。
初めの頃ほど驚いてはいないが未だにこの変身は慣れていなく、
自分が中年の男になっているというのに違和感を感じる。
クローゼットにかかっている洋服を両側に分けるとエレベーターがひっそりとしていた。
変身したサオリがクローゼットに足を踏み入れたとたん、
エレベーターがお入りなさいと言ったように扉が開いた。
中に入ると自動的に閉まり、ブーンと言って降下をし始めた。
下に降りれば降りるほど、どんどん過去にいっているような気がする。
初めはサオリの見慣れた街がガラス越しに見えたが、
しだいに知らない街に移り変わって見えないくらいの速さになった。
見えないくらいの速さといっても、
エレベータの動きはいつもどおりで怖さを感じないがやっぱり不安だ。
ある程度降りた後すこしだけ止まり、数分後には横走りになって動き始めた。
感覚でいえば、時代ではなく今度は国が移り変わっているようだ。
そういえばあのお婆さんはどこの国の人だろう?フランス、ドイツ、イギリス人なのかな・・・
そんな想像を膨らませていると、知らないうちに着いた。
エレベータの扉はガシャーンと、調子の良い音を出しながら開けられる。
ほっ、と胸を撫で下ろし、エレベータの外に一歩足を踏み入れた。
* story *
こくりこくりと寝ているときもあったが後ろに座っている友達が起こしてくれたので、
なんとか最後まで授業の話を聞くことができた。
授業終了後のHRが終わると、ん〜と言ってサオリは腕をいっぱいいっぱいに伸ばした。
「はぁ、終わった、終わったぁ!」
担任の先生が教室から出ていったあと、すぐに他の生徒達が立ち上がり教室が騒がしくなった。
生徒達のすることはまちまちで、黙々と帰りの支度をしたり一箇所に固まって雑談をしたり
ファーストフードやカラオケに誘ったりしている。
「いやぁ〜、先生の話を聞いてると勉強が分かりやすいなぁ。
明日もサボらずに授業をうけようっかな」
勉強の苦手だったサオリは、ようやく勉強をするコツを掴むことができた。
試験の直前なんかに勉強をするよりも、
日頃まじめに授業の話を聞いている方が負担もなく効率的に良いのだ。
「こんなことだったらもっと早くから気づけば良かったな!
徹夜までしていた自分が馬鹿らしいと思うよぉ〜」
今まで自分のしてきた要領の悪さを、腕を組みもって噛み締める。
「サオリぃ、早くしないとおいていくよー」
はっ、と気づいたときに、マナミ達は教室のドアの前から呼んでいた。
いつのまにか3人とも早くから帰る用意をして待っているみたいだった。
「えっ、あっ?ちょ、ちょっと待ってぇ〜。もう、早いんだよぉみんな!」
慌てて机の上に出した教科書やシャープペンシルをそのまま鞄にしまいこみ、
マナミ達のいるところまで小走りした。
友達と帰り道で別れたあと、駆け足で自宅に向かった。
「ただいま!」
玄関で脱いだ靴を跳ね飛ばしていきそうになったが、
何かを思い出したのかサオリは踵を返す。
いつもお母さんに注意されていることだからそろそろ直していかないとねっ、
と言って転がった靴を揃えた。
「おかえりなさい。今日は早くに帰れたのね」
さっきまでテレビを見て寛いでいた母は、リビングから出てくる。
母が玄関前までついたときに、綺麗に揃っている靴を見て驚いた。
「あら、いつもは靴を脱ぎ散らかしていくのに今日のあんたは偉いわねぇ」
うんうんと軽く頷いて感心をしていた。
「えっへん、日頃の自分は怠っているという事に気づいてね、
今日から改めようとおもってたのよ」
すごいでしょっ、と言って腰に手を当てる。
「いいことじゃない。それが長続きすればもっといいのにね〜」
うっ・・・図星だ。母はサオリの性格を知り尽くしている。
「こう見えても私は継続型だよ。私はするまでが遅いけど、
腰を上げるとハイパーになるんだから」
母は娘をからかって楽しんでいた。
「じゃあわたし、これから部屋で勉強をするから」
「ええ、わかったわ。今度の通知表の成績が上がっていたら、
お祝いをしてあげましょうかね」
「わぉ、お祝いお祝い!わたし、回転寿司にいきたいなぁ」
いいよと言ってくれることを期待するサオリは、母の周りでスキップをする。
「いいわ、その分たっぷりと勉強をするのよ」
「ハァーイ」
サオリはルンルン気分で階段を駆け上がり部屋にいった。
変身しているところを誰かに見られてはまずいので、
急いでカーテンを閉めドアに鍵をかける。
ごそっと、机の引き出しの中からネクタイピンを取り出す。
このネクタイピンは父のいらなくなったものであり、
魔法使いはこれに魔法をかけて変身できる道具にしたのだ。
ピンは外に出されて鈍い光を放っている。
「今日はお婆さんのところにいけるわ。待っててね、お婆さん」
ずっと孤独に自分を待ち続ける老婆の姿を思い浮かべてピンを翳した。
「メルトンジェ・ザトゥー・ムーフォス・ラントイア!」
どこの国の言葉か分からない魔法の言葉を唱えると、
ピンから強い光が放射されサオリの体がその光に包まれる。
自分の部屋だとは思えない光景になり、
周りの光の粒子が走っているように見えた。
いつのまにかサオリは浮いており、見下ろすと粒子が底から湧き上がっている。
強い風が吹かれているが、温かくて優しく包んでくれるような心地よいものがあった。
サオリの若々しい姿が徐々に皺が増え、ほどよく老け込む。
膨よかな女性らしい体つきが、
脂肪が減りうっすらと骨がみえるくらいゴツゴツとした体つきになった。
小柄な少女の肩が広くなり、身長が伸びて男らしい体になる。
白無地のシャツ、スラックス、蝶タイ、サスペンダー、背広などの正礼装を身にまとって
シルクハットを被ったあと、最後にステッキと手袋を身につけた。
徐々に湧き上がっていた光が薄くなっていき、変身が終わったことが分かる。
ベッドの傍にあるクローゼットを開け、扉の後ろについてある全身鏡で確かめた。
初めの頃ほど驚いてはいないが未だにこの変身は慣れていなく、
自分が中年の男になっているというのに違和感を感じる。
クローゼットにかかっている洋服を両側に分けるとエレベーターがひっそりとしていた。
変身したサオリがクローゼットに足を踏み入れたとたん、
エレベーターがお入りなさいと言ったように扉が開いた。
中に入ると自動的に閉まり、ブーンと言って降下をし始めた。
下に降りれば降りるほど、どんどん過去にいっているような気がする。
初めはサオリの見慣れた街がガラス越しに見えたが、
しだいに知らない街に移り変わって見えないくらいの速さになった。
見えないくらいの速さといっても、
エレベータの動きはいつもどおりで怖さを感じないがやっぱり不安だ。
ある程度降りた後すこしだけ止まり、数分後には横走りになって動き始めた。
感覚でいえば、時代ではなく今度は国が移り変わっているようだ。
そういえばあのお婆さんはどこの国の人だろう?フランス、ドイツ、イギリス人なのかな・・・
そんな想像を膨らませていると、知らないうちに着いた。
エレベータの扉はガシャーンと、調子の良い音を出しながら開けられる。
ほっ、と胸を撫で下ろし、エレベータの外に一歩足を踏み入れた。
 * story *
エレベータから降りたとたん、扉が閉まり壁に同化した。
帰りはよろしくねっ、と言い残したあと城内を見回す。
床には燕脂色のビロードが敷かれてあり、前を見ると右に階段、左に居間がある。
居間から甘い匂いが風に運ばれて来た。
この匂いを知っている、これはお婆さんが焼いているクッキーの匂いだ。
何度か口にしたことがあるが、
自分の母が作るクッキーとまた違う美味しさを感じた記憶がある。
今日もお婆さん、お爺さんのために焼いて待っているんだね。
そう考えると、胸がしめつけられる思いになる。
サオリはゆっくりと居間に向かって進んだ。
居間は天井が高く大きな部屋で、大時計やショーケース、暖炉などの
古さを醸し出すアンティーク家具が置かれてある。
居間に入ると、焼きたての匂いが部屋の中を優しく包んでいた。
四面の壁にある窓から光が差し込み、居間を明るくしている。
その一つである正面の窓際で、老婦人が椅子に座って本を読んでいる。
ゆっくり近付くと、気配を感じたのか老婦人が立ち上がり笑顔で迎えてくれた。
「おかえりなさい。丁度帰ってくる頃だと思ってクッキーを焼いておりましたのよ」
手で示したところに、レースが掛かった丸テーブルがあり、
その上にクッキーや紅茶が並べてあった。
今日は城に来れたが学校の部活とかで来れなかったときには、
いつもお婆さんはどうしているのだろう。
淋しい思いをして一人で食べている老婦人の姿を想像してしまい、
涙がこみ上げてきた。
「お婆さん!」
サオリは胸が一杯になり、老婦人のもとに駆け寄って抱きしめてしまった。
「あっあなた、どうしたのですか」
抱きつかれた拍子に眼鏡が落ちかけた老婦人は、愛する夫の目の前で顔を紅くしてしまった。
「だっ、大丈夫ですか?何かあったのなら私に言ってくださいな」
それでも老婦人はなんとかして、心配の言葉をかけれた。
ようやく自分が無我夢中にしてしまったことに気づき、慌てて腕を放し涙を拭った。
「すまなかったな、おまえに逢えて嬉しかったものだからついしてしまったことなんだ」
顔を少し紅らめさせながら帽子を脱いで老婦人に謝る。
「おほほ、そうだったのですか。何事かと思い心配しましたが、
あなたの気持ちがとても嬉しかったですよ」
突然のことだったので息をついていたが、とても嬉しそうにしていた。
帽子と背広は向こうにかけておきます、
あなたは椅子に腰をかけてくださいなと言われたので脱いで渡してから座る。
クローゼットにしまってから、こちらに戻ってお菓子を食べる用意をしている。
「今日はアッサムティーなのです。ストレートにしても美味しいからきっと喜ぶかもよ」
花柄のカップに紅茶を注いだりしている老婦人の姿は、とても楽しげだった。
「う〜ん、良い香りだ。飲むのが楽しみだね」
彼女が自分の分も淹れ終えて、椅子に座ってから2人で飲んでみた。
色と香りは濃厚で高級感を醸しだしており、
飲むとふわっと口の中で広がる上品な香りが溢れ出す。
後味も優雅で、ほのかな甘みのある香りが口の中に残った。
「味が濃厚で美味しいね、これはどこかで買ったものかね」
「ええ、これは取り寄せたものですよ。この近くに紅茶専門店がありますの」
「ほぉー、凄いじゃないか」
「うふ。この紅茶はインドのアッサム地方でつくられたから、"アッサム"といいますのよ」
「そうだったのか、ということは他の" ダージリン"とか"ウバ"も地方の名前なのか?」
「そう。ダージリン・ニルギリはインドの、
ウバ・ヌワラエリヤ・ディンブラはスリランカの地域名ですの」
老婦人は紅茶に詳しく、紅茶の歴史などの話に花を咲かせた。
話を聞きながらクッキーを一かじりしたが、
クッキーも引けをとらないぐらいの美味しさだった。
さくっとしたバタークッキーであり、
食べるとバターの優しい香りが口の中に拡がり甘い味がする。
そのうえ、こうやって話をしながら食べるクッキーの味は、
また格別で実に美味しいものがあった。
「おまえの焼くクッキーはいつも美味しいなぁ〜、また作ってくれるかね」
「もちろんいいですわよ、
今日のあなたは特に美味しそうに食べてくださったから作った甲斐がありましたわ」
お腹をさすって満足そうにしている夫の姿を見て、嬉しそうに老婦人は紅茶を飲む。
「そうそう、2日ほど前にお客様が来ましたの」
紅茶カップを置いてから何かを思い出したかのように言った。
「ん?誰かな」
「いえ、初めてくるお客様だったけど、
可愛らしいお嬢さんでした。とても親切な子で私の話に付き合ってくれましたの」
老婦人は窓越しに遠い目で空を見ていた。きっとサオリのことを思い出しているのだろう。
「また来てくれるといいんですがね・・」
窓の隅から一羽の白バトが飛んできて、それが二人の目に留まった。
優雅に羽ばたくハトは、窓の外の城に着地する。
くちばしで毛繕いをしているところを、ぼんやり眺めながらサオリは言った。
「あぁ、きっと来ると思うよ(またお邪魔をさせていただきます、お婆さん)」
二人で見ていたハトはしばらくしてから別の場所に飛んでいった。
* story *
エレベータから降りたとたん、扉が閉まり壁に同化した。
帰りはよろしくねっ、と言い残したあと城内を見回す。
床には燕脂色のビロードが敷かれてあり、前を見ると右に階段、左に居間がある。
居間から甘い匂いが風に運ばれて来た。
この匂いを知っている、これはお婆さんが焼いているクッキーの匂いだ。
何度か口にしたことがあるが、
自分の母が作るクッキーとまた違う美味しさを感じた記憶がある。
今日もお婆さん、お爺さんのために焼いて待っているんだね。
そう考えると、胸がしめつけられる思いになる。
サオリはゆっくりと居間に向かって進んだ。
居間は天井が高く大きな部屋で、大時計やショーケース、暖炉などの
古さを醸し出すアンティーク家具が置かれてある。
居間に入ると、焼きたての匂いが部屋の中を優しく包んでいた。
四面の壁にある窓から光が差し込み、居間を明るくしている。
その一つである正面の窓際で、老婦人が椅子に座って本を読んでいる。
ゆっくり近付くと、気配を感じたのか老婦人が立ち上がり笑顔で迎えてくれた。
「おかえりなさい。丁度帰ってくる頃だと思ってクッキーを焼いておりましたのよ」
手で示したところに、レースが掛かった丸テーブルがあり、
その上にクッキーや紅茶が並べてあった。
今日は城に来れたが学校の部活とかで来れなかったときには、
いつもお婆さんはどうしているのだろう。
淋しい思いをして一人で食べている老婦人の姿を想像してしまい、
涙がこみ上げてきた。
「お婆さん!」
サオリは胸が一杯になり、老婦人のもとに駆け寄って抱きしめてしまった。
「あっあなた、どうしたのですか」
抱きつかれた拍子に眼鏡が落ちかけた老婦人は、愛する夫の目の前で顔を紅くしてしまった。
「だっ、大丈夫ですか?何かあったのなら私に言ってくださいな」
それでも老婦人はなんとかして、心配の言葉をかけれた。
ようやく自分が無我夢中にしてしまったことに気づき、慌てて腕を放し涙を拭った。
「すまなかったな、おまえに逢えて嬉しかったものだからついしてしまったことなんだ」
顔を少し紅らめさせながら帽子を脱いで老婦人に謝る。
「おほほ、そうだったのですか。何事かと思い心配しましたが、
あなたの気持ちがとても嬉しかったですよ」
突然のことだったので息をついていたが、とても嬉しそうにしていた。
帽子と背広は向こうにかけておきます、
あなたは椅子に腰をかけてくださいなと言われたので脱いで渡してから座る。
クローゼットにしまってから、こちらに戻ってお菓子を食べる用意をしている。
「今日はアッサムティーなのです。ストレートにしても美味しいからきっと喜ぶかもよ」
花柄のカップに紅茶を注いだりしている老婦人の姿は、とても楽しげだった。
「う〜ん、良い香りだ。飲むのが楽しみだね」
彼女が自分の分も淹れ終えて、椅子に座ってから2人で飲んでみた。
色と香りは濃厚で高級感を醸しだしており、
飲むとふわっと口の中で広がる上品な香りが溢れ出す。
後味も優雅で、ほのかな甘みのある香りが口の中に残った。
「味が濃厚で美味しいね、これはどこかで買ったものかね」
「ええ、これは取り寄せたものですよ。この近くに紅茶専門店がありますの」
「ほぉー、凄いじゃないか」
「うふ。この紅茶はインドのアッサム地方でつくられたから、"アッサム"といいますのよ」
「そうだったのか、ということは他の" ダージリン"とか"ウバ"も地方の名前なのか?」
「そう。ダージリン・ニルギリはインドの、
ウバ・ヌワラエリヤ・ディンブラはスリランカの地域名ですの」
老婦人は紅茶に詳しく、紅茶の歴史などの話に花を咲かせた。
話を聞きながらクッキーを一かじりしたが、
クッキーも引けをとらないぐらいの美味しさだった。
さくっとしたバタークッキーであり、
食べるとバターの優しい香りが口の中に拡がり甘い味がする。
そのうえ、こうやって話をしながら食べるクッキーの味は、
また格別で実に美味しいものがあった。
「おまえの焼くクッキーはいつも美味しいなぁ〜、また作ってくれるかね」
「もちろんいいですわよ、
今日のあなたは特に美味しそうに食べてくださったから作った甲斐がありましたわ」
お腹をさすって満足そうにしている夫の姿を見て、嬉しそうに老婦人は紅茶を飲む。
「そうそう、2日ほど前にお客様が来ましたの」
紅茶カップを置いてから何かを思い出したかのように言った。
「ん?誰かな」
「いえ、初めてくるお客様だったけど、
可愛らしいお嬢さんでした。とても親切な子で私の話に付き合ってくれましたの」
老婦人は窓越しに遠い目で空を見ていた。きっとサオリのことを思い出しているのだろう。
「また来てくれるといいんですがね・・」
窓の隅から一羽の白バトが飛んできて、それが二人の目に留まった。
優雅に羽ばたくハトは、窓の外の城に着地する。
くちばしで毛繕いをしているところを、ぼんやり眺めながらサオリは言った。
「あぁ、きっと来ると思うよ(またお邪魔をさせていただきます、お婆さん)」
二人で見ていたハトはしばらくしてから別の場所に飛んでいった。
|





